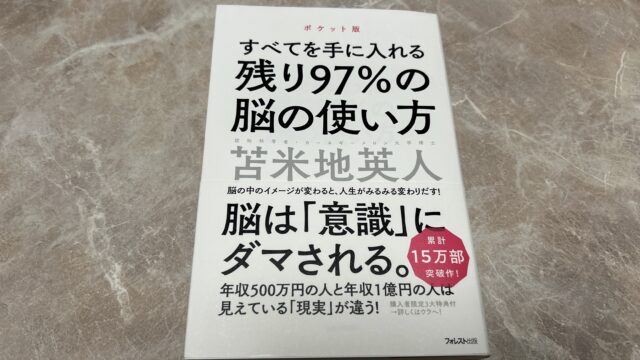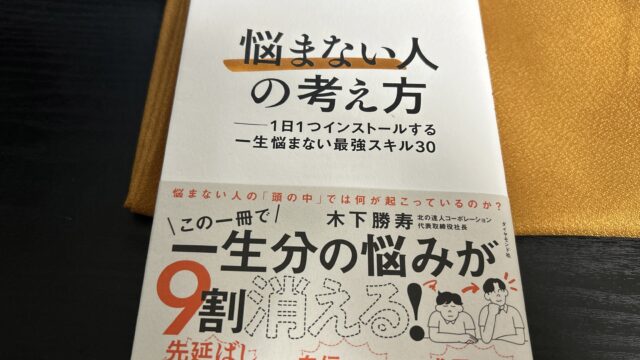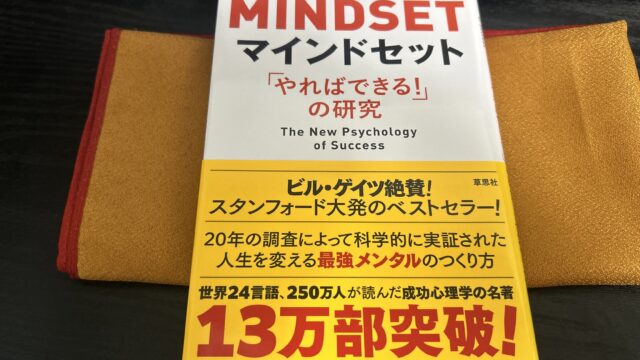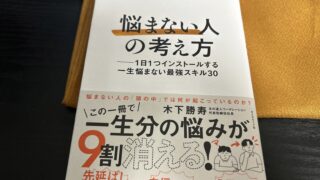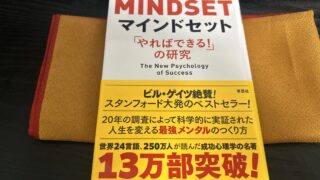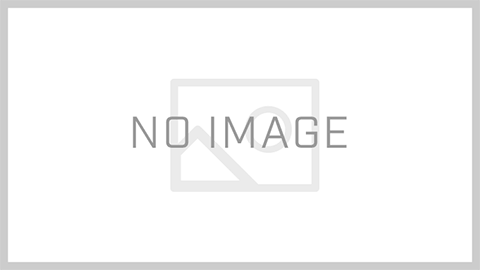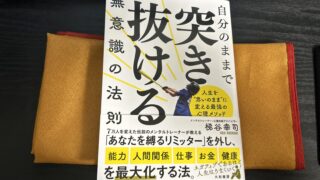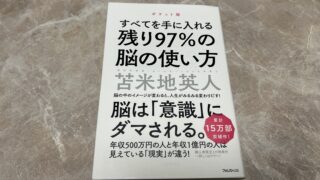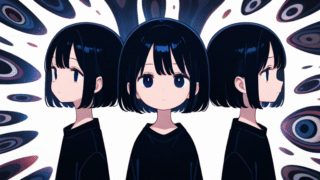心のサーモスタット
人として生きる以上、普段の生活の中では様々な感情を持っていることと思います。明るい感情もあれば、暗い負の感情もあるでしょう。特に、自分の負の感情に支配されてしまい、思い悩んでしまうことはないでしょうか?私はしょっちゅうあります。プレゼンがうまくできず自分を責めたり、無愛想な態度の店員さんに嫌気が差したり・・・。挙げ出すとキリがありません。
ここでは、「悩まない人」の考え方(著:木下勝寿)に書いてあった、自分の負の感情に対する思考アルゴリズム「心のサーモスタット」を紹介します。この考えを身につけ、「事実」を「思考」することで、自分の感情に悩まされなくなり、少しでも悩みから開放されることでしょう。
書籍【「悩まない人」の考え方】については、こちらの記事で紹介をしています。
https://wtr-dynamics.com/【書籍紹介】「悩まない人」の考え方/
心のサーモスタット とは
心のサーモスタットという考え方は、悩まない思考アルゴリズムの1つとして紹介されていました。これは、マイナスの感情によって生じる悩みをすぐに解消する方法でした。何かマイナスの感情を感じた時に、その感情に流されたり、長引かせたりせず、その原因となる「外部・出来事・事実」を「思考」するというやり方です。特に、不快な感情が大きいほど、ひどい経験ほど、悩みかけている自分に気付きやすいはず。「感情モード」から「思考モード」に切り替え、不快な感情の原因を思考します。日頃から自分の感情を観察することこそ、悩まないための重要な方法です。
サーモスタットとは、ある一定の温度に達すると「カチッ」とスイッチが切り替わり、「これ以上温度を上げるのをやめよう」という機能です。電気ケトルなどを想像するとわかりやすいです。心のサーモスタットも同様で、ある一定以上の強いマイナスの感情を感じ取ったら、「感情モード」から「思考モード」に頭のスイッチを「カチッ」と切り替える機能ということですね。
心のサーモスタットは、人が社会で生きるために欠かせない機能?
この心のサーモスタットという機能は、感情に振り回されて悩むかどうか以外にも、人が生きる上で大変重要な機能ではないかと思いました。例えば、ニュースで物騒な事件が報道されていたとして、その事件の犯人に対してあなたはどう思うでしょうか。「バカなことをするなぁ」などと思うでしょうか。少なくとも、私はそのようには思いません。それどころか、(少々極端かもしれないですが)「明日は我が身かもしれない」とまで思います。(もちろん、進んで事件を起こそうなどとは思いませんが…。)
あろうことに、人間は「感情次第でいくらでも非合理的な行動を取ってしまうことがあり得る」生き物です。これは人間の抱える致命的なバグのようなものです。
怒りに流されて心にも無い一言を言ってしまったり、怠惰によりすべきことを先延ばしにしたりといった具合でしょうか。これにより、思わぬトラブルが起きるかもしれません。ニュースで報道されている事件の犯人は「感情モード」に振り回された結果、何か事件を起こしてしまったのかもしれません。ひとたび感情モードに振り回されてしまうと、最悪、社会から排除されてしまうこともあり得るということです。そう考えると、人が社会で生きるということはあまりにも綱渡りのように思えます。その命綱として機能するものが、心のサーモスタットではないでしょうか。
・基本は論理的合理性のもとに生きる
・それでも負の感情が出てきてしまう時には、全ての発言・行動をやめ、徹底的に思考する
・感情に身を任せて動く前に、その感情の元にある事実に立ち返って、合理的に物事を判断する
この節で書き綴ったことは、実は私がたまに使う「1時間集中」する時に書いてアウトプットするためにノートに書いていた内容を参考にしました。(こんなことを真面目に考えたこともあったのですね…。)
おわりに
悩みを0にすることは難しいかもしれませんが、感情に対する思考法を身につけることで、ある程度の悩みは解消されるかもしれません。やはり、このような思考法は実践あるのみ可と思います。知っていることとできていることは別物なので。
同じ本の中に書かれている、一見独立した考え方同士が滑らかに繋がること。他の本に書かれていたことと組合わせることで、更に深く理解できること。これを実感できた時、読書の楽しさを感じると思います。また、本の中の1フレーズについて深掘りすることで、そこから新たな気づきや学びがあることも発見でした。